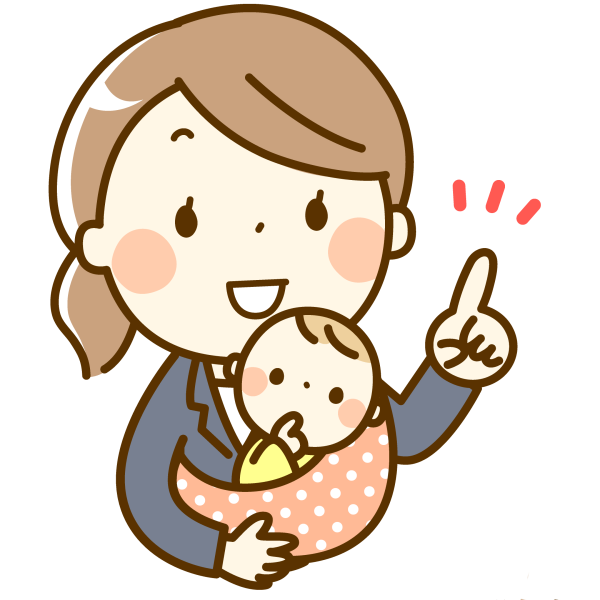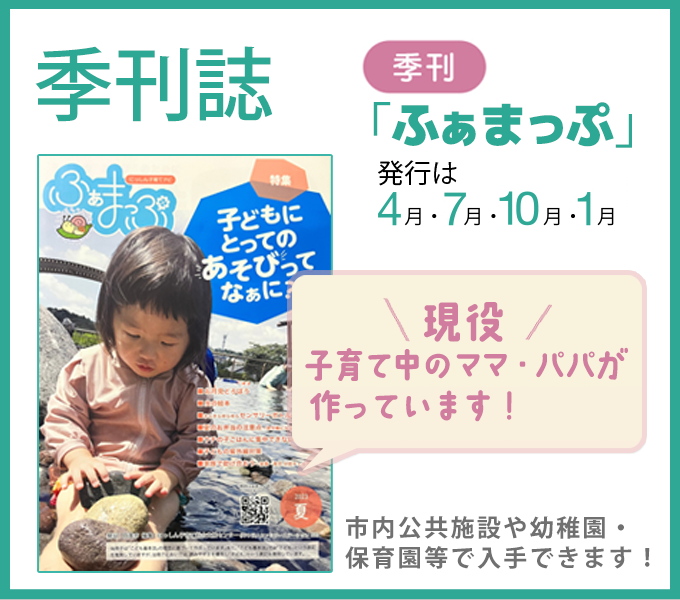こども未来戦略(※)に基づき、2025 年4 月より、育児休業等給付に「育児時短就業給付金」と「出生後休業支援給付金」が新たに創設されました。今回は、「育児時短就業給付金」についてご紹介します。
1.支給を受けることができる方(受給資格・支給条件)
受給資格
①2歳未満の子を養育するために、雇用保険の被保険者であること
②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12 か月あること
各月の支給要件
③初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
④1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
⑤初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
⑥高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
支給対象となる時短就業
育児時短就業とは、2歳に満たない子を養育するために被保険者からの申し出に基づき、事業主が講じた1週間当たりの所定労働時間を短縮する措置です。厚生労働省ホームページ掲載の「育児時短就業期間等に係る証明書 週所定労働時間算定補助シート」を活用して確認できます。フレックスタイム制、変形労働時間制など特別な労働時間制度の適用を受けている場合も同様です。
2.支給額
原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額が支給されます。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。 また、各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額 を超える場合は、超えた部分が減額されます。
▼次の①~③の場合、給付金は支給されません。
①支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準と比べて低下していないとき
②支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上であるとき
③支給額が最低限度額以下であるとき
3.支給を受けることができる期間(支給対象期間)
給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の 属する月までの各暦月について支給されます。
▼以下の①~④の日の属する月までが支給対象期間となります。
①育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日
②産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
③育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日の前日
④子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日
厚生労働省のホームページ「育児休業等給付について」を参照しています。
誌面の都合で、詳細な説明を省いています。詳しくは、下記厚生労働省のホームページやリーフレットにより確認ください。
育児休業等給付についてはこちらです。
育児時短就業給付(厚生労働省リーフレット)はこちらです。
※子ども未来戦略
2023 年に子ども子育て支援の充実のために国が策定した戦略
①若者・子育て世代の所得を増やす
②社会全体の構造や意識を変える
③すべてのこどもと子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援していく等を基本理念とする。