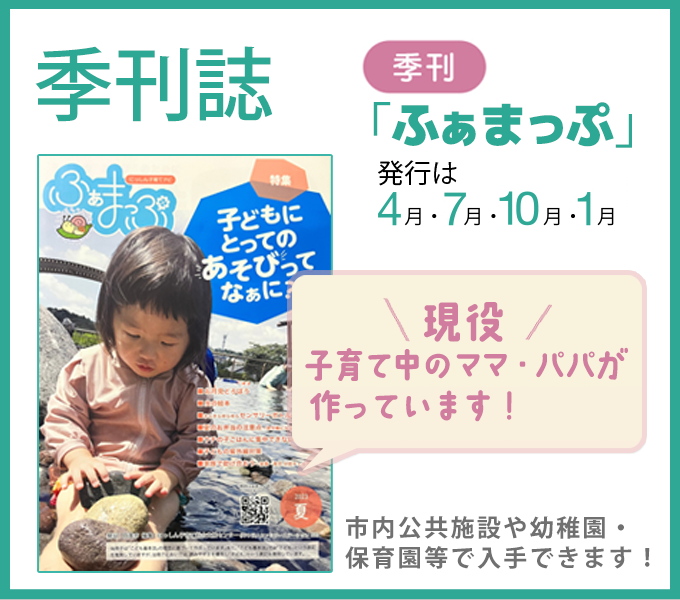いまや私たちの日常生活の一部となっているスマホやゲーム機。
子どもにとっても身近な存在になりつつあり、乳幼児の時期から触れる機会もあるのではないでしょうか。
子どもが好きな動物の鳴き声を調べたりするなど便利に活用できる一方、ネット依存など心配なことも多いですよね。
スマホなどを触りはじめる乳幼児の時期に、どのようなことに気をつけたら良いのか、名古屋学芸大学のヒューマンケア学部子どもケア学科幼児保育専攻教授(併任) 子どもケアセンター長 渡辺桜先生にお話を伺いました。
遊んであげたいけど大人も家事などで忙しい。スマホに頼らずひとりで遊んでくれるようなヒントは?
最初は余裕のある時に大人がいっしょに遊びます。
一度やれば次からは少しお手伝いするくらいでできるようになっていきます。少しずつ、その遊びの引き出しを増やしていきましょう!
Point.1 子どものやりたい気持ちを引き出しましょう。
●特別感を出しましょう。効果音も忘れずに。「今日は特別に、デデーン!大きな新聞紙で遊ぼう!」
●あえてじらして出しましょう。声のトーンも変えてみるのもアリ。「なんと・・・カレンダーの裏にお絵描きしていいよ!」
●大人が楽しそうに遊んでみせましょう。
Point.2 ひとりで遊んでいるときも見守りましょう。
●何かをしていても、子どもの遊んでいる様子が視界に入るように体の向きを変えましょう。
●声をかけたり、目配せしたりしましょう。お絵描きをしていたら「その色好きだよ」と声をかけたり、目があったら「いいね!」と目配せしたりすると、『見守ってくれている』と感じて子どもも安心します。
例えばこんな感じ

子どもがひとりでも遊べるような遊びの引き出しをたくさん作ってあげましょう!
例えば…
●新聞紙やチラシをまるめる
(まるめた新聞ボールとペットボトルでボーリングができますよ♪)
●小麦粉粘土
●カレンダーの裏にお絵描き
例えば …
※『◯歳児 室内遊び』とインターネットで検索すると、アイデアがたくさん出てきます。
お子さんが好きそうなものを見つけて、その出し方を工夫することで、遊びたい気持ちを引き出しましょう。
ママパパだけでなく、おじいちゃんおばあちゃんや友だちのママパパと遊ぶと遊びの種類がもっと広がります。
でもやっぱりスマホやテレビを見る時は
・それぞれの家庭でのルールを決める(大人も守る)
・ルールは子どもといっしょに決める
・子どもの成長に合わせてルールを見直す
・最初は大人も一緒に使ったり、見たりするなどして良い見本を見せる
テレビや動画を見るときも1 人で見るのではなく、誰かとコミュニケーションをとりながら楽しむことを覚えてもらいたいですね
うちでもやってみました!
いつもならお風呂に入りたがらない子どもたちに対して、「何に変身して行く?ぴょんぴょんうさぎさん?」と言って早速誘ってみました。
すると2 歳の娘はぴょんぴょんで行くと言い、5 歳の息子はカエルで行くと言って、すんなりお風呂に向かってくれました。こんなに乗ってくれるのには驚きです。リズム共有によって、子どもも大人も明るく楽しく過ごすことができると感じました!
子どもと接するときはもちろん、家事をしているときも、オノマトペを口にしながら一つ一つ動作をすることが日課になりました。子どもは6か月なので、まだ言葉のやり取りはできませんが、オノマトペのリズムが面白いのか、これまで以上に、言葉を聞いて笑ったり、じっと見てくれるようになりました。そんな反応を見るのも楽しく、これまでは必死にこなしていた家事も、楽しみながらできています。